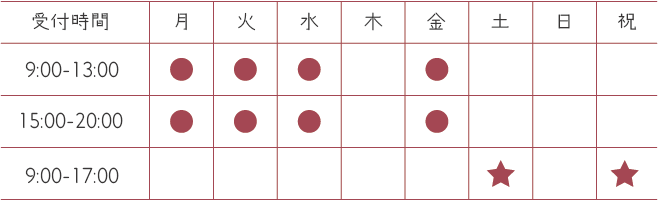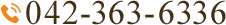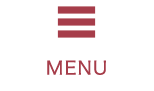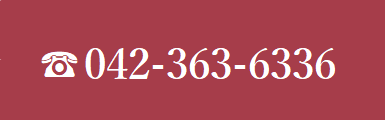紅茶でインフルエンザを撃退!
今年もインフルエンザが流行していますね…困ったモンです。
今回のブログは「紅茶でインフルエンザ感染を防ぐ方法」をお伝えします!
1、茶に含まれるカテキン類が発酵過程で変化し「紅茶ポリフェノール」が生まれ、この成分がインフルエンザウイルスの感染力を奪います。
2、通常飲む濃度でOK。インフルエンザウイルスの感染性をわずか15秒で99.9%失わせることが可能です。
3、インフルエンザウイルスは、毎年変化しています。昨年のインフルエンザには免疫があっても、今年のインフルエンザには効力がないということもあります。
紅茶ポリフェノールは生きたウイルスに吸着能力を発揮。A型(トリ、ブタ、ウマ、ヒトを含む)、B型、昔のウイルス、今の新型まで、全てのインフルエンザの型に顕著な効果が認められます。
4、感染してから熱が下がるまで、平均3〜4日間を要しますが、ウイルスの排出は4〜6日後まで続いています。熱が下がったからといって治ったわけではなくウイルスを周囲に撒き散らしている状況に変わりはありません。
インフルエンザ予防の要は、「人からもらわない、人にあげない」こと。熱が下がっても、口腔内に残っているインフルエンザウイルスを紅茶で失わせることができれば、周囲の家族など、健康な人への感染予防に大きく貢献します。
5,インフルエンザのシーズンは、マスク、手洗いとともに、紅茶を飲む習慣をつけましょう。
流行の広がりを抑えることができれば、学級閉鎖も減るものとと推測します。
「ストレート」か「レモン」で摂取しよう。ミルクティーでは紅茶の有効成分の紅茶ポリフェノールがミルクのタンパク質に取り込まれてしまうため、ウイルスの感染力を奪う効果がなくなってしまいます。同様に、豆乳(大豆タンパク)、マシュマロ(卵白・ゼラチン→ともにタンパク質)も感染力阻止の効果がなくなる可能性があります。ミルクティーを楽しみたい場合は、最初の1、2口をストレートで味わってから、ミルクを入れていただく方法をお勧めします。
砂糖、はちみつはOK。
ホットでもアイスでもOK。
皆さんは紅茶にこんなパワーがあるなんて知っていましたか!? 紅茶パワーで予防に努めましょう(^▽^)
※日本紅茶協会ホームページを参照
ストレスフリーになる方法part2
今回は前回からの続編をお伝えします(^_^)v
人間には体内時計というものが備わっていて、朝起きて日の光を浴びるとセロトニンが分泌されて覚醒のスイッチが入り、日中には昼間の活動に必要なホルモンや、暗くなってくると神経を和らげ眠りに導くホルモンが自動的に高まっていきます。
まるで電車の時刻表のように、一日の中でさまざまな脳内物質やホルモンが適切に機能するよう制御されています。 もし、何の前触れもなく電車が10分遅れたらどうなるでしょう。大きな事故に繋がりますよね。
人間の体も全く同じで、毎日規則正しい生活を送ること、日々の行動をルーティン化することが心身の健康に直結します。
毎朝決まった時間に起きて、決まった時間に散歩することは、体内時計をリセットする意味があります。つまり朝散歩には、私たちの中に組み込まれている時刻表に則って脳や体が機能するよう、整える効果もあるのです。
その為に先ず改善すべきは「睡眠時間」と「睡眠の質」です。
次回はその事についてお伝えさせていただきます(^^)/~~~
ストレスフリーになる方法
オンとオフの切り替えが上手にできる人を「ストレスフリー」と言いますが、この切り替えがうまくできない人が増えています。
今回のブログは「ストレスフリーになる方法」についてお伝えしていきます!
オンからオフへの切り替えは脳内の前頭前野で行われ、幸せホルモンとも言われる「セロトニン」が分泌されます。 精神を安定させ幸福感を得やすくする、意欲や集中力を高める作用があります。
そのセロトニンの分泌量を高める方法として
1、朝の散歩。陽の光が目の網膜に入ることで活性化され、ウォーキングのようなリズミカルな運動もセロトニンの分泌を促すので、朝起きてから15分程度、太陽を浴びながら歩くだけでも効果的。セロトニン神経によって脳が覚醒し、さらにバナナ1本でも摂っておくと、血糖値が上がって体もスムーズに始動できます。
2、昼は屋外へ出て再び日の光を浴び、青空の下で食事や休息するのもリラックス効果があります。
3、会社帰りには、ジムなどで軽い運動をするだけで分泌効果があります。
これらを習慣にすることで日中はセロトニンが十分に分泌され、日が沈むと眠気をもたらしてくれる睡眠に不可欠な「メラトニン」というホルモン物質に代わります。
次回へ続く…
~年末年始のお知らせ~
12月29日(日)~1月3日(金)まで休診とさせていただきます。
ご不便をお掛けしますが宜しくお願いいたしますm(__)m
1月4日(土)午前のみ~診療スタートです(^▽^)関節がポキポキ鳴るのは何故!?
今回のブログは「関節が鳴るのは何故!?」というテーマでお伝えしていきますね!
皆さんもストレッチ等で関節を動かすと「ポキポキ」と音が鳴るという経験がありますよね?骨折しているわけでもないのに、音が鳴るのは何故でしょうか…
2018年3月に科学的に証明した論文が有名な科学専門誌に掲載されました。
「関節の中には関節を曲げたり伸ばしたりしやすくするために滑液という液体が含まれていて、関節を曲げると滑液中の圧力が変化し、滑液に溶けていた気体が泡になることがある。その泡がはじけることでポキっと音が鳴る」とのこと。
ポキポキの音は100年以上前から泡が弾ける音だろうと言われてはいたのですが、科学的に解明しても役に立たないだろうということで医学界でも放置されていたとのこと。 この論文を発表したアブドゥル バラカト教授のこの研究のきっかけは息抜きと、たまたまだったそうです(^_^;)
ただし関節を鳴らすことがストレッチの目的ではありません。 関節を無理に動かしたり勢いをつけてひねったりすることは、正常な可動域を超えて動いてしまい、ケガや慢性的な痛みにつながる危険性もあるので、無理のない強度で行いましょう(^_^)v
動的ストレッチ実践編!
今回のブログは「動的ストレッチの実践編」についてお伝えしていきますね!
前回は動的ストレッチの3つのメリットをお伝えしました。 今回は実際のやり方やポイントなどについてお伝えしていきます。
動的ストレッチを行う際、回数は特に決まりはありませんが、各種目10~15回を目安にイタ気持ちイイ程度まで伸ばすのが基本です。
効かせるポイントとしては、慣性でカラダを振るのではなく、伸ばしたい筋肉の反対側にある筋肉(拮抗筋)の力を使って動かすことが重要です。
例えば、太もも裏の筋肉を伸ばすために、脚を前に振り上げる動作であれば、股関節前側の筋肉で脚を引き上げる意識で行います。 これは、拮抗筋の力を使うことで「相反抑制」という生理特性を利用できるのがその理由です。 相反抑制とは、活動する筋肉の反対側にある筋肉を脱力させやすくする反射現象の一種です。この相反抑制を利用して筋肉の力を抜きながら行えるのが、動的ストレッチの最大の特徴です。
今回はちょっと難しかったかもしれませんが…
朝や運動前は動的ストレッチ、運動後や就寝前は静的ストレッチ、というように使い分けると効果的だと知っておくと役立ちますよ(^.^)
動的ストレッチのメリットについて
今回のブログは「動的ストレッチのメリット」についてお伝えしていきますね!
ストレッチは、姿勢を止めたまま行う静的(スタティック)ストレッチと、軽く勢いをつけて体を動かしながら行う動的(ダイナミック)ストレッチがあります。
2種のうち本日は動的ストレッチのメリットをお伝えします。
1、実動作における可動域を高められる!
静的ストレッチを行っている時とスポーツ時における可動域は必ずしもイコールではありません。運動中に力んでしまうと実動作における可動域が小さくなってしまう為です。 動的ストレッチでは、動作の中でタイミング良く脱力する練習になるため、静的ストレッチで得た柔軟性を実動作の可動域に繋げる為に取り入れましょう。
2、カラダを温めながらストレッチを行える!
動きを止めながら行う静的ストレッチに対して、動かしながら行う動的ストレッチは軽い運動にもなるのでカラダを温める効果もあります。
3、コンディショニング効果が期待できる!
動的ストレッチを行うと、急性的に筋力やパフォーマンスが向上するというデータがある為、運動前のウォーミングアップにも適しています。
次回のブログでは実際のやり方をお伝えしていこうと思いますのでお楽しみに(^ ^)
~臨時休診と振替診療のお知らせ~
10月21日(月)~22日(火)臨時休診のため連休となります。
本来は休診日である24日(木)振替診療します。
変則的な日程になりご不便をお掛けし申し訳ございませんが宜しくお願いいたしますm(__)m
ストレッチの効果について
今回のブログは「ストレッチの効果」についてお伝えしていきますね!
ストレッチにはカラダを柔軟にする効果がありますが、「一過的(急性)効果」と「長期的(慢性)効果」に大別されることは知っていますか⁉
一過的効果とは「効果がすぐに表れ、すぐ元に戻る」という意味。 ストレッチを行った直後に可動域が広がる「コンディショニング効果」を狙い、運動前のウォーミングアップに取り入れられる事が多いですね。 一過的な柔軟性をもたらす要因は、筋肉が脱力しやすくなるからです。 なお、持続時間はおよそ30分程度で元に戻るとされていますので、持続時間を考慮して行いましょう。
長期的効果を得るためには、ストレッチを継続的に行うことです。 継続的に行うのは、本質的に可動域が広いカラダへと変化させる「トレーニング効果」の狙いがあります。 長期的な柔軟性向上をもたらす要因は、筋肉が材質的に柔らかくなる、関節構造が柔らかくなるからです。
このようにカラダを改善するには、近道はなく、継続することが大切なのだということが分かりますね…「継続は力なり」です!
10年後も健康でいられるようにコツコツ続けていきましょう(‘ω’)ノ
~夏季休暇のお知らせ~
8月18日(日)~8月22日(木)まで休診とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが宜しくお願いいたしますm(__)m
8月23日(金)から通常診療です。